
 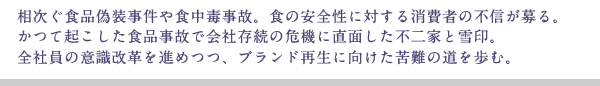 『ミシュランガイド京都・大阪2010』で3つ星を取得した京都吉兆社長の徳岡邦夫は、ここ2年ほどかつてない危機感に襲われていた。 大阪の船場吉兆で賞味期限(その期間内ならおいしく食べられるとする表示)や産地の偽装事件が発覚したのが2007年。百貨店などで販売していた菓子のラベルを張り直して賞味期限を偽装したり、消費期限(おおむね5日以内に消費すべき食品への表示)切れの総菜を別の店に流したりしていた。また、九州産の牛肉を「但馬牛」、ブロイラーを「地鶏」などと表示して販売するなど、偽装が幅広く行われていたことが明らかになった。 さらに翌年、客が食べ残した料理を使い回していたことが発覚し、高級料亭としての信用は地に落ちた。刺し身、アユの塩焼き、天ぷら、八幡巻き、たたみいわし、フルーツ寄せゼリー…。使い回していた食材が次々に明らかになるにつれ、料理人でもある徳岡は次第に怒りを抑え切れなくなった。 船場吉兆と京都吉兆の間には資本関係は一切ない。経営もそれぞれが独立している。吉兆創業者・湯木貞一の教えを引き継ぎ、京都吉兆3代目として日本料理の魅力を1人でも多くの客に伝えようとしてきた徳岡にとって、料理を冒涜する行為は何よりも許しがたかった。 しかし、火の粉は徳岡の元にも降りかかってきた。「同じ『吉兆』なんだから、どうせおたくも同じようなことをしているんでしょう」。ある客から言われたこの言葉に、徳岡は大きな衝撃を受ける。予約のキャンセルが相次ぎ、百貨店などでの総菜や贈答品の販売額も激減した。一種の風評被害に遭ったわけだが、一蓮托生の吉兆ブランドの失墜は、想像以上のダメージを及ぼすことになった。 「バブル崩壊の時もお客様が減ってかなり苦しんだが、今回の場合は単に経済的な理由だけでなく、ブランドに対する信頼そのものを失っただけに、より傷は深い」(徳岡) 徳岡はこの危機を乗り切るために組織の体質を変える経営改革が必要と考え、人材の強化に舵を切り始めた。船場吉兆の問題は、長年の同族経営の馴れ合いや甘えがもたらしたと考えているからだ。いつまでも主人と使用人といった関係を引きずっていてはいけない。大卒の社員を初めて採用し、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語が話せる社員を揃え、外国客への対応にも力を入れている。これまで同族が占めてきた役員も、今後は社員の中から登用していく考えだ。 また、「一般の方から見れば料亭は秘密のベールに包まれて近寄りがたいイメージがあり、料亭の側もそれが店のステータスと勘違いしてきたところがある。そうした閉鎖性や秘密主義が不祥事のはびこる温床になっていたのではないか」と考え、情報公開にも取り組んでいる。社員に対して経営の状況を報告し、これまでなかった広報部門を設けた。弁護士や会計士にオブザーバーになってもらい、外からの目で経営をチェックしてもらっている。 今回得たミシュランの3つ星は、吉兆ブランド再生に向けて力強い援軍と期待される。だが、「たとえ風評被害だったとしても、お客様のイメージはそう簡単には覆らない。社会に必要な存在にならなくては店が生き残れないんだという危機感を、ずっと持ち続けていたい」と気を引き締めている。 |
雑誌名:日経ビジネス2009年11月9日号 信頼回復へのイバラ道