
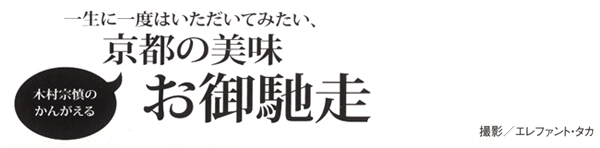  (1)安くておいしい。 (2)安くてまずい。 (3)高くておいしい。 (4)高くてまずい。 「この中で最も悲しいのは?」、それは②「安くてまずい」店に行き当たった時です。「値段も安いし、まずいだろうな…」と思って暖簾をくぐったら、果たしてまずかった。このア・プリオリな感情は、わが身の責任で、だれを責める訳にもいかず、それはそれは悲しいもの。 では、「最も喜びと幸せが大きいのは?」と尋ねられた時の答えは?賢明な読者諸姉はおわかりと思いますが、そう、(3)「高くておいしい」お店です。この理屈、実はコラムニスト神足裕司さんによるもので、かつて一世を風靡し、物議も醸した料理ガイドの奇書『恨ミシュラン』の一文がオリジンです。衝撃でした。一読して即、私自身の御馳走の店選びの指針となり、以来その価値観が揺らいだことはありません。 やはり、あらゆるハードルを越えて「高くておいしい」店は御馳走のメッカ、聖地、総本山です。物理的に、値段が高いことに意味などありません。高いからおいしいのではないからです。値段など気にせず最高を求める困難、それを克服するから価値が生まれるのです。そもそも、高いフィーを支払うお客の要求は当然ながら高度になるもの。お店側は、自分で自分のハードルを上げてるようなものです。喜ばせてくれて当たり前、おいしくて当たり前といった具合に。お店側に落ち度でもあった日には、落胆どころか〝攻撃〟がほとんどでしょう。最高級のタイトルを維持するのは並大抵のことでないと思います。 だから、御馳走とは?を考えるとき〝スノッブ〟呼ばわりされる危険を冒してでも、高くておいしい料亭やグランメゾンは外せません。第一、あれこれ理屈をこねて非難するよりそういうお店にあこがれるほうが素直です。そこで、京都を舞台に稿を進めてきた本連載が、満を持しておすすめする高くておいしいお店が、かの京都吉兆さん。 洛西、嵐山。渡月橋や天龍寺といえば中学生でも知っている景勝地。大堰川の畔にたたずむ屋形の冠木門には、名前の大きさからするといささか控えめな表札がかかっています。数寄屋の贅を凝らした建物と季節の移ろい豊かな庭が調和した空間は、〝庭屋一如〟のお手本とも言うべき美しさ。名料亭の手本と評されるのもうなずけます。ただ、私がこちらを押す一番の理由は、空間美や料理の質だけではありません。 初めて訪れるにふさわしい「料亭」かもしれない、と思うその理由、建築や献立を超えるであろう魅力とは、お店のスタッフの姿勢です。「屋形」とも言われ、お座敷で食事をする料亭では、食事の最中に料理人さんと直接コミュニケーションをとることは稀です。そこで問題になるのが「仲居さん」を筆頭にしたお店のスタッフの方々。部屋のしつらえから料理の名前までわからないことだらけの初心者が、慣れない間にまず怯えるのはこうした人々とのやりとりではないでしょうか。 |
雑誌名:SAVVY 2010年2月号 98〜99P / 刊行元:株式会社 京阪神エルマガジン社