
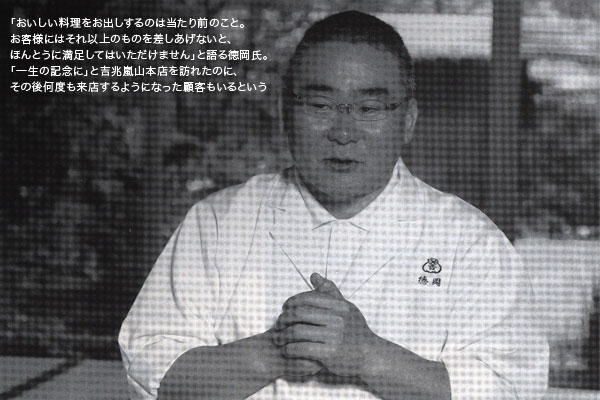 考えてみると、そもそも京都に観光にいらっしゃるお客様は、非日常の空間と時間を求めているような気がします。高い天井のあるお寺や、空まで続く錯覚を覚える借景のお庭。そして、一日二十四時間は変わらないはずなのに、なぜかゆったりと流れているような気がする時間……。こうした非日常を味わいたくて、多くの観光客の方々が京都に足を運びます。 |
雑誌名:THE21 2010年2月号 74〜77P / 刊行元:PHP研究所
 |
|
|
|
|
雑誌名:THE21 2010年2月号 74〜77P / 刊行元:PHP研究所 |