
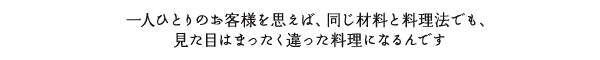 感涙のサービスのためにもう一つ心がけていたのが、お客様一人ひとりを思いながら料理をつくることです。たとえば八十歳のおばあさまと二十歳のお孫さんが来店されたとします。コースを注文されたなら、まったく同じ料理をお出しするのが普通かもしれません。しかし、八十歳と二十歳では、嗜好(しこう)や身体が心地よいと感じる味が根本的に違うはずです。ご高齢の方なら、オイリーなものよりさっぱりしたものがいいだろうし、歯も弱くなっているかもしれないので、食べやすいように薄く切ってお出ししたほうがいい。材料を薄く切れば盛りつけは変わるし、盛りつけが変われば、それに合う器も変わります。つまり一人ひとりのお客様を思えば、同じ材料と料理法でも、見た目はまったく違った料理になるわけです。 |
雑誌名:THE21 2010年2月号 74〜77P / 刊行元:PHP研究所