
|
徳岡 本を読んで衝撃を受けました。科学的な考えのもとに料理を考えることは、すごく意味があると思います。100gの野菜がコースに含まれていたというのは、人間が生きていくうえでの心地よさ、求めているものを経験のうちに表現していたのかもしれないですね。どんなご馳走も続けば不味く感じるようになる、それは人間に備わった本能というか。かつおとコブを組み合わせればイノシン酸とグルタミン酸の相乗効果でうま味成分が8倍になるというのも、経験でもう知っていたわけですね。日本で取れるたくさんの食材から選んで、組み合わせ、うま味という言葉にした。イノシン酸、グルタミン酸の組み合わせは世界中にあり、トマトやチーズにも含まれています。それをうま味という言葉にしたことが、日本人の優れたところかと思います。 だしの作り方も、西洋のフォンなどは長い時間をかけて中のエキスをできるだけ出すのですが、日本は一瞬です。だしを取る素材の完成には長い時間がかかりますが。長い時間だと雑味も出てしまう。濃い味付けにしないと良さが発揮されないのです。ピュアなうま味がスーッと出る、日本の方法は健康にもいい気がします。コトコトと骨の苦味まで出すのは、それがおいしいという意見もありますが、苦味は毒でもありますから。 稲垣 苦味は毒だというのは面白いですね。 徳岡 苦味は毒だから50種類くらいレセプターがあるんじゃないかな。デトックス作用があるのも苦味ですね。毒素が体にたまってくるとデトックス効果のあるものを食べたくなる。生きるために必要なものを、脳が欲するのでしょうね。 稲垣 確かに、年いくほど苦いものが食べたくなりますね。子どもの時は嫌だったのに。不思議なものですね。 徳岡 自分は本当はどうしたいのか、って思いながら食生活を送るのが一番いいのかもしれません。 菅野 (お吸い物が来て)お吸い物に胡椒を使われるのですね。和食に胡椒、というのには驚かされました。 徳岡 驚きもおいしさだったり、海外の方にも普通に食べていただけます。日本料理のボーダーは、なくなってきているでしょうね。 |
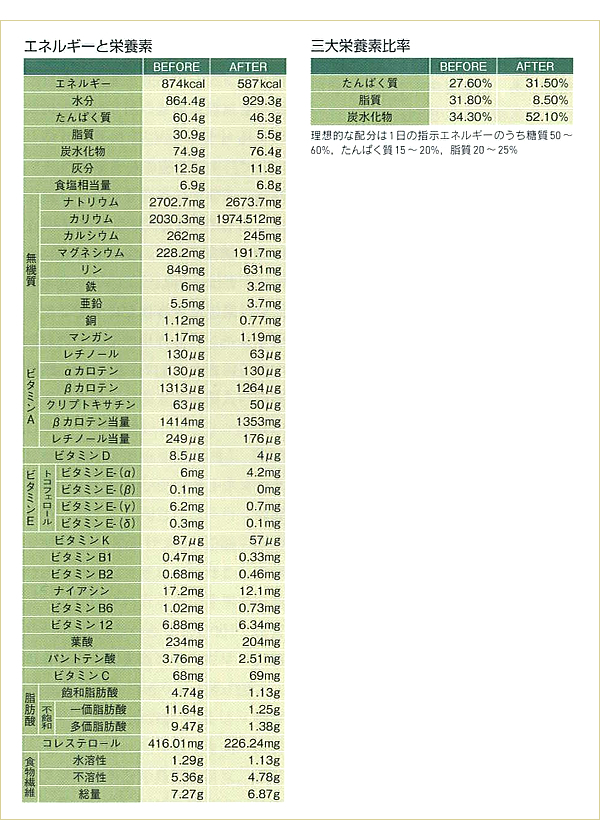 |
|
稲垣 先程、ここは非日常だとおっしゃった。確かにそうですね。患者さんの生活を縛りすぎれば、治療意欲を失わせることにもなります。クリスマスやお正月、非日常は生活するうえで大切です。逆に言うと、非日常をいかにうまく使うか。 徳岡 宇宙食をやらないか、というお話があったのです。エネルギーを取るだけの食事だと精神的にダメになって、宇宙飛行士も任務を放棄して帰りたいと言うそうです。それで、食事で非日常を演出するものができないか、と。まずは見た目の改善を、など提案しましたが、今予算を減らしているようで話自体がなくなりました(笑)。病気を治すという目的を遂行することにも、リンクする気がします。食事はエネルギーを補充するだけでなく、メンタル的なケアを含んでいるのではないでしょうか。 菅野 糖尿病食も続かない方が多いのですよ。退院後2~3ヵ月でダウンされる。それで、自分の気持ちを上向きにするために食べたい物を食べる日をつくることを提案することがあります。1食だけなら制限なしに食べてもいい、とか。 徳岡 余裕ができるんだ。 菅野 それなりにセーブをされるのですね。 稲垣 それが“今日は吉兆の日”効果ですね。非日常に向けて準備をするし、そのために努力もする。 菅野 目標を決めるのはいいことだと思います。 |
雑誌:Islet Equality 11月号 35~39ページ / 刊行元:ノバルティス ファーマ株式会社