|
|
 |
|

食は健康を支える礎。そして、おいしく食べることは、心も豊かにしてくれる。人が「おいしい」と感じるのはなぜか?そもそも「おいしさ」とは何か?現代の食と健康について、日本を代表する料理人、京都吉兆嵐山本店総料理長の徳岡邦夫さんと、「おいしさ」の謎を追究する科学者、伏木亨・京都大大学院教授が語り合った。絶品の味を生み出す側と、その味の秘密を探る側。相対する立場から「おいしさ」に挑む2人の対談を2回にわたり、紹介する。
--伏木さんは「おいしさ」を、生理的なもの・食文化・情報・本能--という4種類に大別されます。
伏木:生理的とは、のどが渇いた時の水、汗をかいた後の塩分など、体が欲するものがおいしいという仕組みです。食文化は、子供のころから食べ慣れた味をおいしく感じるもの。多くは地域性があります。ふな寿司やくさやなどのおいしさはこれに当たります。
情報のおいしさはCMや街のうわさ、店先の行列などの「おいしそうな情報」が脳の扁桃体という部分に作用して生まれます。本能でおいしいと感じる食材の代表は脂肪と砂糖とだし。これらを食べると脳でβエンドルフィンという快感を与える物質がでます。快楽の食べ物、ドラッグのように「やみつき」になるおいしさですね。
徳岡:日本料理の要がそのだしですね。多くは昆布とかつお節のいわゆる「一番だし」です。昆布、かつお節のほかは塩、しょうゆ、水と具材というシンプルな材料で作った煮物碗が日本料理屋さんの顔であり、味の基本です。私たちの店では、コースの2品目に煮物碗をお出ししています。そこでお客さまの味の好みをお聞きして、その後の料理の味を全部調整していきます。お客さまもだしの味で自分の好みか否かを判断されていると思います。
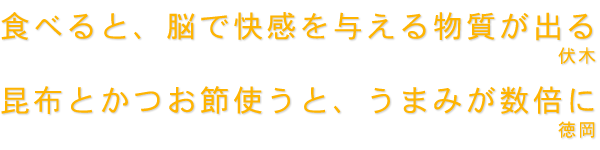 --西洋にもだしはありますよね。
--西洋にもだしはありますよね。
伏木:世界中にあります。だしの本質はうまみで生物が生きるために必要不可欠なアミノ酸と核酸が作る味なんです。だからおいしい。ただ、だしは材料や作り方で風味が変わります。日本は昆布だし、東南アジアはニョクマムやナンプラー、ヨーロッパにはガスパーチョというトマトのスープがあります。トマトに含まれるアミノ酸の一種、グルタミン酸のうまみを生かしただしですね。
徳岡:グルタミン酸とイノシン酸(核酸の構成物質)は、舌にあるうまみの受容体への結合を互いに強め合うという作用がありますよね。だからだしの中にこの2種類が同時に存在すると、うまみが数倍に跳ね上がります。一番だしは昆布のグルタミン酸、かつお節がイノシン酸。鯛の昆布締も同じ仕組みでおいしいんですが、この理論を踏まえればいろいろな料理のバリエーションが生まれます。
例えば、昆布を粉末にしてお作りに振りかければ、お作りの昆布締め。普通の昆布締めは鯛の水分が昆布に奪われますが、この方法ならそれが防げます。また鯛の代わりにチーズでもいい。組み合わせの工夫で新しい「おいしさ」が作れます。
伏木:なるほど。魚を含む動物の肉にはイノシン酸が含まれますからね。実はグルタミン酸で起きるうまみの相乗効果は、その詳しいメカニズムが未解明で、現在のホットな研究テーマです。 |
| |
|
|
 |