 痩せて眼ばかりが鋭い青年、湯木貞一が大阪の新町に初めて自分の店を持ったのは昭和五年、二十九才の時である。店の間口は二メートル足らずで、奥行きは六メートル。十人も入れば息をするのも窮屈になるほど狭い店だった。店の名前は近所にあった今宮戎神社のシンボル、吉兆笹からとった。ただし、吉の字の上の部分は武士の士ではなく、食べ物を育む大地の意を含ませて「土」にした。こうして「御鯛茶處 吉兆」は産声を上げたのである。その後、店は拡張し、畳屋町へ移る。同時にメニューも増え、日本料理屋となった。しかし、畳屋町の店は、昭和二十年三月十三日の空襲で全焼、灰燼に帰したのである。湯木が本格的な店を再建したのは昭和二十二年のことで、それが高麗橋にある吉兆本店だ。 痩せて眼ばかりが鋭い青年、湯木貞一が大阪の新町に初めて自分の店を持ったのは昭和五年、二十九才の時である。店の間口は二メートル足らずで、奥行きは六メートル。十人も入れば息をするのも窮屈になるほど狭い店だった。店の名前は近所にあった今宮戎神社のシンボル、吉兆笹からとった。ただし、吉の字の上の部分は武士の士ではなく、食べ物を育む大地の意を含ませて「土」にした。こうして「御鯛茶處 吉兆」は産声を上げたのである。その後、店は拡張し、畳屋町へ移る。同時にメニューも増え、日本料理屋となった。しかし、畳屋町の店は、昭和二十年三月十三日の空襲で全焼、灰燼に帰したのである。湯木が本格的な店を再建したのは昭和二十二年のことで、それが高麗橋にある吉兆本店だ。
その後、湯木貞一は京都の嵐山、東京の木挽町と出店を続け、平成九年、九十五歳で亡くなるまでに全国に十九の店を設けた。

料理人としての湯木貞一は生涯、チャレンジャーであった。彼の本質は伝統を守りながらも、料理に新しい趣向を導入することにあったのである。例えば松花堂弁当も湯木貞一が発案したものだ。彼が岩清水八幡にある松花堂招乗の庵を訪ねた際、形のいい煙草盆を見つけた。それに向う付けや刺身を入れ、お椀をつけたのが松花堂弁当なのだ。
またフォアグラやキャビアといった西洋料理の食材を日本料理に持ち込んだのも彼がはじめてである。もっと言えば、現在うまみ調味料と呼ばれるようになった味の素や昭和三十年代までは誰も見向きもしなかった
冷凍の食材を家庭の主婦に推薦したのも彼である。
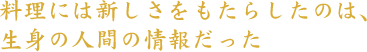
では、こうした新しい情報を湯木はどうやって手に入れたのだろうか。食に関するジャーナリズムが確立していなかった当時、湯木が頼ったのは活字ではなく、生身の人間だった。彼は店のなかに座っていることなく、つねに一流の才能たちとつき合っていたいのだ。料理研究家の辻静雄、『暮らしの手帳』の名編集長・花森安雄、写真家・入江泰吉といった人々はその代表だろう。彼はこうした人々を大切にし、情報を摂取しながら伝統に安住しない吉兆の料理を作り上げていってのだ。
吉兆は日本料理を代表する店ではあるが、伝統を墨守するだけの保守的な料理屋ではない。その生い立ちの頃から、変化を求める革新的な料理屋だったのである。 |