物選びをするうえで、上を見ればきりがない。でも、どうせ夢を見るならとことんまでゆきたい。 今や海外にまでその名を轟かせる「吉兆」の料理道具を拝見させてもらうことにしました。 訪れた先は「吉兆嵐山本店」。 今さら説明するまでもなく、昭和5年に近代の日本料理の父といっても過言ではない湯木貞一氏が、大阪で開業したお店がことの始まり。 現在は三代目にあたる徳岡邦夫さんがきりもりしている。 取材スタッフは、石庭に面した部屋へと通された。均整の取れた幾筋もの「線」と「円」の織りなす模様が、実に耽美的な石庭だ。ほどなくして徳岡さんが一束の箸を持って現れた。
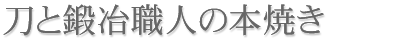
「盛り付けなどに使う箸は、自分で作ります」 まず、吉兆のご主人は、どこぞの名のある名人が作ったであろう「包丁」などではなく、「さい箸」を開示したのっだ。 一暼。市販のさい箸とあまり、変わらない。 一触。感触は、いい。 「山から竹を取ってきて乾燥させ、荒削りから仕上げまで、すべて手作り。吉兆ではある竹藪と契約していて、そのこの竹を使ってるんですよ」 凝視。普通のさい箸と比して、短い。
「これはさい箸といっても、家庭で料理をするときに何にでも使うようなさい箸とはちょっと違い、先ほども申しましたが、主に盛り付けに使います。油ものにはまた別の長い箸を使います」 注視。いささか、太い。
「太さに関しては経験上のもの。ある程度、太さがあったほうが楽なんですね。先は細くなっていてぴっちり合わされますので、細かい仕事も問題なくできます。自分が使う箸を自分で削るというのは、結局は自分の使いやすいように使いたいからでして。包丁もそうですよね。自分が使いたいように自分で研ぐわけです−」
湯木貞一氏の著書『吉兆味ばなし』「(家庭向けの日本料理本。大さじ何杯とかいわれるレシピは、ほとんど記載されていない希有な本である。とはいえ、きちんと読めばそこいらの料理本とは比べものにならないほど、実際の料理に役立つから不思議。その昔は「へたな嫁入り道具を持たせるくらいなら、この本を持たせたほうがいい」とまで言われた名著)のなかに包丁について触れた箇所がある。
<包丁を持って、おろし場にたつときは、やはり本焼きの包丁を持ちたいですね> 「本焼き」とは、日本刀を作るときと同じ鋼と鉄を使い、さらに工程を簡素化した霞(かすみ)というものもある。 「和庖丁」はこの「刀と同じ」という点が肝らしい。鍛冶職人が槌で真っ赤に燃えた地金をカンカン叩く、まさにあれのこと。その何度も叩いては鍛えるやり方が、洋包丁との差異を生む。畢竟するに、この作りが和包丁の「キレ」「堅牢性」、ひいては刺身の切り口などに見受けられる、日本料理独特の「切り口の美」へと昇華するのだ。
物選びをするうえで、上を見ればきりがない。でも、どうせ夢を見るならとことんまでゆきたい。 今や海外にまでその名を轟かせる「吉兆」の料理道具を拝見させてもらうことにしました。 訪れた先は「吉兆嵐山本店」。 今さら説明するまでもなく、昭和5年に近代の日本料理の父といっても過言ではない湯木貞一氏が、大阪で開業したお店がことの始まり。 現在は三代目にあたる徳岡邦夫さんがきりもりしている。 取材スタッフは、石庭に面した部屋へと通された。均整の取れた幾筋もの「線」と「円」の織りなす模様が、実に耽美的な石庭だ。ほどなくして徳岡さんが一束の箸を持って現れた。
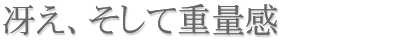
徳岡さんは我々の前に三本の包丁を並べた。
出刃。
菖浦。
薄刃。
この三本が和食を作るうえでの基本の包丁となる。
出刃は魚をおろすのに使う包丁。菖浦は刺身用の包丁で、柳刃とも言う。薄刃は野菜を切るためのもの。菜切りとも呼ばれるものだ。
使い込まれた柄の部分がえぐられている。菖浦だけは柄の部分をつけ替えたばかりのようで、えぐられてはいない。刃の部分はどしりと鈍色を湛えていた。その包丁の凄みを前にして、下世話にも「やはり名のある庖丁なんですか?」と問うた。「先代が刀師に作らせたものです。それを譲り受けました。
柳刀に関しては堺の同じく刀師に作っていただいたものですが…まあそれよりも、料理人にとってその包丁が使いやすいかどうかが大事でして。僕は包丁の重心を意識してます。先に重さがあって、ある程度その重さを意識して切れるものが好みです。重心がほんのわずかに変わってしまうだけで、使い心地は違ってくるものなんです。
あとは何より手入れが大切です」徳岡さんは、包丁の研ぎ方についてたっぷりと講義してくれた(ハイレベルな叙説で、素人にはマネのしようもない。ほんの触りだけお伝えすると、包丁一本の中で刃先、真ん中、手元と、三つのステージでそれぞれ研ぎ方が違うそうだ)。ちなみに、湯木氏が「本焼き」にこだわる理由はこう記してある。
<冴え、重量感、刃こぼれのできないもの、一度もってみたら、それがよくわかりますし、わかるから大事にします。丁寧にも研ぎます。>
包丁の要諦な素性にあらず。ご両人は口を揃えて、扱い方が大事だと仰せなのだ。
|