|
|
 |
|
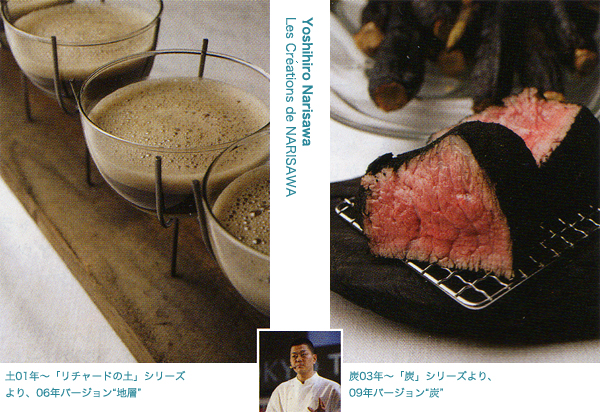
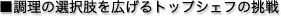
3日間の中で、最も観客を釘付けにしたのはイギリスのヘストン・ブルメンタルの発表だった。調理機器として誰も見なかった濃縮機や濾過器といった研究室用の道具を早くからキッチンに持ち込み、科学的なアプローチを高度に昇華してきたシェフの筆頭である。科学と聞くと冷たいイメージ、そして発表内容も実験室の様な空気を思い浮かべそうになるが、この日のデモンストレーションはまるで違っていた。舞台上のスクリーンでは、料理が誕生するまでの背景がまるで長編小説のように編まれ、壮大なストーリーがひと皿の中に流れていることを観客は知らされる。キリスト教の東方の三賢人、不思議の国のアリス、祖父の部屋の香り・・・思いもかけないテーマが創作の対象として取り上げられ、科学的アプローチの助けを借りながら次々と料理へ姿を変えてみせるのである。最終的に、科学は料理を難しく考えるためではなく、表現の可能性を広げるための選択肢のひとつであるという着地点に観客は導かれた。
 |
| |
|
|
 |