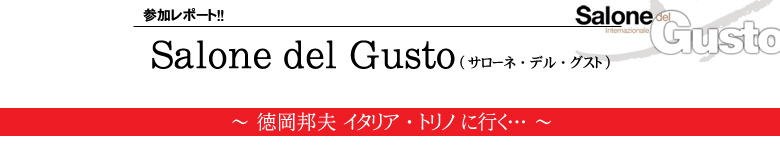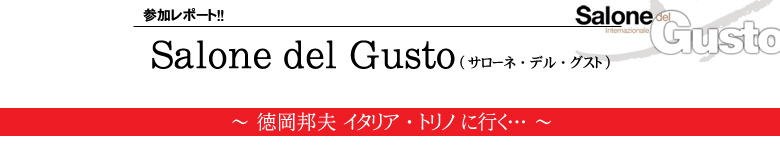〜MENU〜
Text Kunio TOKUOKA
Photo Chiiho SANO
Menu(Italian) Sayaka MIYAMOTO
古来より日本人は、季節の移り変わりを感じられる感性を大事にしていきました。その感覚が優れた人が才能のある人と認められてきました。自然の移り変わりを人の気持と重ね合わせて表現してきたからだと思います。和歌や茶道、香道などあらゆる日本文化の根元となっています。日本料理においても、そういう手法が今尚使われています。特に吉兆では、その表現方法で情熱をお客様に伝える事を大事にしています。
テーブルセッティングに関して
日本では、正式な食事をする時「お膳」に自分の料理を置きます。料理を体内に取込む純粋で潔白な物としての扱いをします。その「お膳」の代わりに天然藍染めの布を用意しました。「お膳」の上の箸おき、箸、器、料理、グラスがそれぞれ別の形、別な色をしているのにまとまった空間を作っています。そのコントラストこそが日本的な感性です。
1. お向八寸:花オレンジと和ろうそく 三種
・ スカンピ霜降り、バジリコ 酒盗ソース
・ 鶏皮のカリカリ、ニッツァ・モンフェラート産「カルド・ゴッボ」
・ ひじきとカルマニョーラのペペローニ
2. お椀:鱈と胡麻豆腐
・ 胡麻豆腐
・ 鱈
・ 葉タマネギ
・ 柚
3. 造り:徳岡風ピエモンテ生牛肉
・ ピエモンテ産仔牛肉
・ ジャガイモのピュレ
・ 揚げ米
・ 揚げ大蒜
・ 和辛子
・ 一味唐辛子
・ 浅葱
4. 焚合:ポルチーニ茶碗蒸し
・ ピエモンテ産フンギ・ポルチーニ
・ 生姜と浅葱のペースト
・ 鰹節
5. 焼物:鱈柿の種揚げ(魚の揚げ物 醤油ソース)
・ 鱈
・ インゲン
・ ボルロット種白インゲン豆
・ フローレンス・フェンネル(西洋ウイキョウ)
・ マッシュルーム
・ ルコラ、イタリアンパセリ、バジリコの3種のペースト
・ 柚
6. 御飯:栗御飯
・ クーネオ産マローネ(栗)
・ 生クリームとパルミジャーノチーズのソース添え
7. 菓子:水羊羹と薄茶
・ 水ようかん
・ 抹茶
料理に対する簡単な説明
◆ 八寸(一品目)
始めの料理は、花形の朱漆の器の中に柑橘実で作った小さな器で構成されています。中身は、a) 焼霜海老の酒盗和え、b)
ひじき、c) カルド鳥皮和えです。日本酒と合わせて飲んでください。
八寸とは利休居士が京都洛南の八幡宮の神器からヒントを得て作ったといわれるもので、そもそもは、八寸角の杉のへぎ木地の角盆を意味しました。やがて、それに盛られる酒肴のことを意味するようになり、現在では献立の名称となっています。
◆ 煮物椀(二品目)
使っているお椀ですが、木地を削り部分的に漆を数回塗り固め、そこに金で色々な花の蒔絵が描かれています。
中身は、胡麻から作った豆腐と地中海で取れた焼白身魚です。スープは、鰹節と昆布で取った日本独特のスープ(これを「だし」といいます)に、塩と醤油で味付けをしています。水は、京都の嵐山で使っているのと同じものを、協会の方で調達していただきました。
このだしを取るときに使う昆布ですが、元々は海藻類で、だしに使える昆布になるまでには手間と時間がかかります。また、鰹節を作るには約6ヶ月かかります。様々な行程を経て硬い固まりになります。それを削り、暖めた昆布の出汁にさらすと濃縮な出汁が出てきます。この2つの要素が日本料理のベースを作ります。調味料は塩と醤油です。色々な種類や使い方が有りますが、基本的にはミックスさせる事です。後は、生、焼く、蒸す、焚く、揚げるなどをミックスさせたり、度合いを測る事の組み合わせで出来ています。その辺はどの国も一緒で、その合わせ方やタイミング、食材が各地域で違っているのだと思います。
◆ お造り(三品目)
お造りとは、生の魚のことです。本来は、マグロを使うつもりでしたが、急遽ピエモンテ州の生牛肉を使うことにしました。ワインも出すようにと言う協会の指示ですので、少しEUスタイルにアレンジしてみました。ナイフ&フォークで御召し上がりください。
牛肉には、粉山椒が風味付けされています。揚げた御米とマッシュポテトなどを一緒に御召し上がりください。アクセントに黄色のマスタード、赤い一味を添えてお召し上がり下さい。ぴりっとします。ソースは、オリーブオイルと醤油のブレンドです。
◆ 炊き合せ(四品目)
旬のポルチーニーを炭焼きにしました。暖かい甘くないプリンと一緒に召し上がって下さい。アクセントに、削った鰹節をあしらってみました。微妙に踊る鰹節がコミカルです。ママの料理のように優しい味がするはずです。
◆ 焼き物(五品目)
マグロを醤油と味醂(米から作った甘味料)で付け焼きにする予定でしたが、急遽鱈を使ったメニューに変更しました。柿の種を衣に揚げてみました。醤油との相性が抜群だと思います。
◆ 御飯(六品目)
栗のリゾットです。日本にも奈良時代よりチーズや乳製品が渡来しており、「酪」や「蘇」、「醍醐」と言われていました。当時はあまり普及しなかったようですが、奈良時代の面影を今に活かしてみました。
◆ デザート(七品目)
小豆で作った水羊羹です。こくがあり、どこかチョコレートに似た風味があると思います。抹茶との相性を楽しんで下さい。
|